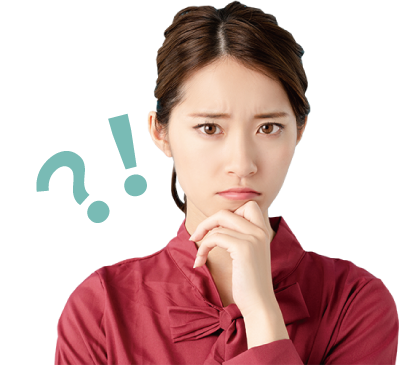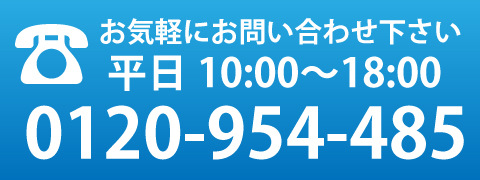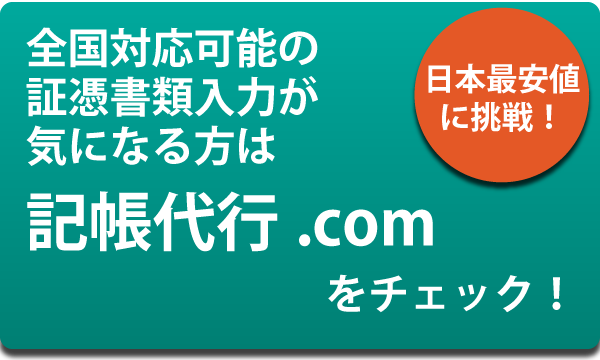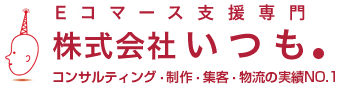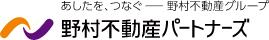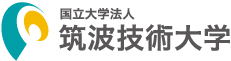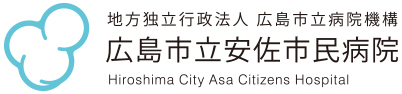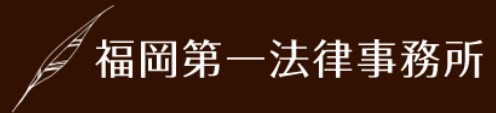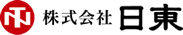目次
当時のイタリアの時代背景
この時期のイタリアは東方との海上貿易で巨額の利益を上げており、現代日本でも使われる単語『リスク』の語源となった船乗り(リズカーレ)達が一攫千金を夢見てヴェニスなどの都市に集まり大賑わいだったそうです。 一度の航海で巨万の富を得られるけれど、その航海の高額の初期費用が自己資金だけでは賄いきれないということで、融資をする『バンコ』現在の銀行という仕組みが誕生し、『借金』や『持ち株会社』という概念が発明されて利益配分が複雑になったために、この問題に対応した『複式帳簿』という記帳方法が生まれました。
複式帳簿とは
1つの取引を借方と貸方に記録する記帳方法で、現金が増えた時は借方に現金の勘定科目と金額を、減った時は貸方に現金の勘定科目と金額を記入します。 この記帳法により現金と所持品目の合計として資産が表せるようになり、船乗りによる商品の中抜きや横流しを防止することができたようです。蒸気革命で生まれた新しい考え方
時は流れて19世紀のイギリスでは、ついに産業革命が始まりました。 中でも特に影響が大きかったのが、蒸気機関の開発による蒸気機関車の登場です。 流通が高速化すれば、それだけ経済も活性化します。 イギリスは国中の木を切り倒し、燃やして燃料に変えて製鉄してまで線路を敷設していったわけですが、そこでひとつの問題に直面しました。 それは鉄道会社の資金調達問題です。 これまでのビジネスとは異なり鉄道会社では固定資産への初期投資が巨額になってきます。 しかも収入はチケット収入に頼るしかないため、開業してしばらくは確実に赤字になってしまいます。 そうなると投資家たちも鉄道会社への投資を躊躇うようになりました。 これに困った鉄道会社の経営者達が編み出したのが『減価償却』という考え方です。 掛かる費用を何年かに分けて予算として計上したのです。 『減価償却』の考え方により費用を分割することで毎回配当金を出すことができるようになり、出資者を呼び込むことに成功したイギリスは、モータリゼーションを世界に先駆けて成功させ、やがて世界の大部分を植民地とする大帝国を築くことに成功しました。 大事業の裏には常にお金の流れがあって、帳簿上の発明が国の行く末を変えたこともあるって考えたら、経理はとてもエキサイティングに見えますよね。